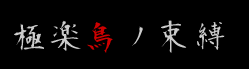【陸話】
上京してきて数ヶ月。
ざわざわと騒音の絶えない人ごみの中、僕は――
沢山の人間が触れ合うか触れ合わないかの距離で傍に居るにも関わらず
自分はたった一人で在る、と云う孤独感を募らせながら歩いていた。
こんなに大勢居るのに、僕は独りだ。
居るのに誰も居ない。認知出来ない。――して貰えない。
それに大して異議が在るかどうかも僕には分かりかねていた。
雑踏の音が響く。人が地面を踏みしめる。生きる力の音だ
しかし皆は当たり前の様にしっかり生きて居る。
どうして僕の足は――
自らの足元をじいと見る、その刹那、人並みに押され、よろけてしまう。
ふらふらと頼り無く歩く、僕の足音は誰よりも儚く、小さく、無力だった。
楽しそうな声が遠い世界の物音の様に脳内に響き、木霊し、
神経が逆撫ぜられ僕は息苦しくなり思わず喉を押さえた。
視界が揺らぐ。体感温度が曖昧になる。
まるで丁度体温と同じ位冷めたお湯に浸かっているかの様に何処までが僕の体で、人の体が認識が出来なくなり
我が身を抱いたつもりだったが、隣の人の服を引っ張ってしまった。
「何するんですか!気持ちの悪い!」
ご婦人が眉間に皺を寄せ、体を引きそう罵った。
「っあ!、、あの――、ああ、あ、、、ん、、、うう、」
息が苦しくて言葉が発せられない。寒くも無いのに体が震える。
忌々しい汗が滝の様に頬を伝い、それでも何とか謝罪をしようと試みるが
見かねたのか相手は気味悪い物を見た、といった顔で後ずさると雑踏の中に消えていった。
一人になると呼吸と心が楽になり、また目の前の現実から逃げる様に思考に潜る。遠くで号外を配る人の声が聞こえる。何か大きな事件でも起きたのだろうか。
――それも所詮は他人事。
大きな事件も、小さな揉め事も、隣人の想いも、幸も不幸も何もかも全てが私から遠く、霞んでいた。
いつから僕はこうなってしまったのだろう。
幼少の頃からこんな奇妙な人間だった、と云う訳では無かった。
友人と外の景色が暗くなるまで遊んでいた時も在った。
その時は僅かな時間でも高らかに笑っていた。
人一倍、楽しい事は好きだった時も在る。いや楽しい事は今でも好きだ。ただその対象が閉じた世界の中にしか向かなくなっただけなのだ。
おそらく原因は慢性的な――脅迫概念にも似た劣等感。
僕は一体どうなれば満足出来るのだろう。
この嫌な感覚から逃げる事が出来るのだろう。
例えばこの雑踏に居る人間が、いや、世界が自分ひとりしか存在しないのであれば何と比べる事が無く、背を伸ばして生きていけるだろうか。
そもそも人は一人で生きれるのだろうか。
少なくとも僕は誰とも接する事も無く生きる事が酷く難しい様に思う。
発作の様に孤独に耐えかねる時が来るし、一人では自分の食料さえ満足に作れない。
だから生きて行こうと思えば、とりあえず食べる為に働く。
人と関わる機会の少ない内職でさえ材料を誰かから貰わねばならないし例え材料を自分で作れたとして、作った物を販売してくれる人が要る。
販売など、社交が苦手な僕に出来る筈が無い。
だから、、一人で生活するべく思考を走らせると必ず手詰まりになって仕舞う。結局僕は他人を嫌いながらも他人と足並みを同じくする羽目になり
それでもなるだけ人と関わらずに済む様な仕事を探して、、今の仕事に辿り着いた。
それだけだ。
――それだけか?
人と関わる為の言い訳に仕事と云う義務を置いているだけで
本当は――僕は酷く人の存在を欲しているのでは無いかと疑う時が在る。
ざわざわと胸に押し寄せる飢餓感に胸を掻き毟る時が在る。
それでも結局この年まで一人を好んでやってきた。
いや、誰も傍に居てくれなかった、それが虚勢を省いた真実だろう。
仕事と言う同じ荷物を抱える事で僕は誰かと居る事になる。
そして僕は孤独から僅かながらに逃げながら孤独を欲する事でその現実をも否定する。
――僕は、、。
胸にチクリと棘が刺す。
自分が誰にも好まれない異形の生物と認めたく無い自分に理解を強要する。
不意に雑踏の音に引き戻されて現実の埃っぽい空気が鼻腔を擽り
僕は僅かながらに顔を上げ、また思考に耽りながら歩き出した。
髪を長くして顔を隠し、背を丸めて息を殺し身を隠す。
誰にも気が付かれる事の無い様に道の端の建物の影に身を寄せながら道を歩くのだ。
人の視線が、怖い。耳を澄ませてしまうと僕に関する罵声、悪言が聞こえて来る気がして耳を塞ぐ。
人ごみの中、僕は怖くなり、足が竦み、終には立ち止まり目を瞑ってしまった。今すぐに忘れ去りたい筈の産まれ故郷の風景が瞼に蘇り、僕を更なる苦痛へと誘った。
山間に位置する農耕の地。閉鎖的な片田舎。
生まれ育った場所にも関わらず、僕の居場所は何処にも無かった。
家に居るのも気詰まりで、村に出るのは恐ろしい。
だから僕は学校と云う社会に出る事にした。
東京の、、生まれ育った息苦しい村から遠い世界へ逃げ出したのだ。
ずっと篭りがちだった僕が学校に行く事を示唆した夜、両親は声を殺して啜り泣いていたのをいつもは愚鈍な僕の聴覚は取らねば良いのに敏感に聴き取ってしまっていた。
彼らの喜びが重苦しくて首が絞まりそうだ。
その喜びの分だけ、彼らは泣いていたのだろうと思うから。
僕の存在が彼らを追い込み、その心を泣かせていたのだろうと思うと腹から何かがこみ上げてきて首元に詰まった。
そうして僕の首は内からも中からも締まってしまい、またその息苦しさが怖くて内へ内へと閉じ篭り人に関しての免疫をどんどん取り零してしまい、また少し人と関わるのが怖くなり、他人が酷く毒々しく見える様になる。
そうして僕は負の螺旋降下から出られなくなる。
如何して僕は素直に愛されている、と喜べ無いのだろう。
自分の心への負荷ばかりが気になってしまう。
何て我侭なのだろう、、僕は自分の醜さに毎時、毎日途方に暮れていた。
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】