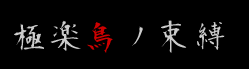【参話】
「お知り合いですか?」
如何にも優男風のその男はハンチング帽を被った英国探偵風の風貌に
野々村と同じ位に長く伸ばされたこれまた直毛な髪を 男は指先でさらりと流しながら私達に対峙し丁寧に頭を下げた。
「初めまして、珠城敬治と申します。絵描きをしております。こちらの――」
と彼は私から見て彼の背後に居た彼に場所を譲る様に斜めに身を引きながら
「現代絵画の巨匠で有(あ)らせられる中尾光造先生の弟子に御座います」と その〝先生〟を仰々しく持ち上げつつ紹介をした。
中尾と云う人物はどうやらこの世界で相当地位の高い人物の様であった。
「お初にお目に掛かります。中尾と申す絵描きに御座います。以後――お見知りおきを。 そしてこっちは画廊の主人をしておる李藤で――」
手のひらで差す様に紹介された銀縁眼鏡は咳払いを一つすると
眼鏡を中指で上げながら神妙な顔で軽く頭を下げた。
反射で眼鏡が光る。余程神経質な男なのだろうか レンズには指紋一つ付いていない様子だった。
「そしてこのつまらぬ雑記ばかり記しておるのが深江と申す絵描き、 これも私の弟子に御座います。」
無精髭に樋口を思わせる尖った短髪、如何にも無骨で禁欲的な印象のその男は メモを持った手を下ろし我々を見据えて深々と丁寧に頭を下げた。
切れ上がった一重瞼が、時代劇に出てくる侍を思わせる風貌だ。
「――どうか見知ってやって下さい」
と家来の紹介を終えた王様の様な堂々たる巨匠は人好きのする気さくな笑顔でそう締めた。
彼の話し方は非常にゆっくりと威厳に満ちた話し方だった。
隙が無く息苦しく感じたのは彼を紹介した珠城と言う人物が相反する様に非常に軽い口調だったからだろう。
「あ、あ、あの、こちらは私の知人で御座います。
帝都大学精神医学研究室教授の六華是終様とその助手の――」
慌てて私の紹介をした蒼井さんの額には薄っすら汗が浮いていた。
緊張で息が続かなかったのだろうか、彼女が言葉を切ると
間を埋める様に 「野々村修一と申します。六華の教え子で御座います。」
と場の空気を察した野々村は襟を正し深々と頭を下げた。
その一連の動作や言葉の選び方が少し心に引っ掛かる。
野良猫同然に家に転がり込んできた時からの違和感。隠し切れない何かを彼から度々感じるのだ。
空気が張り詰めている。
銀縁眼鏡を掛け、中尾の横で控える李藤と云う男は 光るそのレンズの奥に
疲労の所為か濁った目をぎょろぎょろさせながらずっと骨ばった手に握る白い布で額を拭っていた。
無精髭を生やしながらも服装が整っている所為か別段汚らしく見えない不思議な風貌の侍は 中尾の言葉を全て記述しておくつもりなのか始終手帳を開き鉛筆を構えていた。
器用なものだと感心はするがその暑苦しい手袋を取った方が書きやすいのではないかと他人事ながら少し心配をした。
異様な集まりに思えたが、芸術家とはこうしたものかと納得し私は頭を下げ、彼の握手に応えた。
「絵の世界の事は無知なもので、とてもご高名な方とお見受けしました
お会い出来て光栄です。こちらこそ、どうか宜しくお願いします」
「失礼致しました。珠城は如何にも大袈裟でね。
私はそんな対した者では在りません。 古いだけの絵描きに御座います。
如何かお心安くお話し下さい。」
思いの他柔らかく謙虚な姿勢に肩透かしを食らった気がしたが
私も身に余る〝教授〟と云う肩書きに周りが反応する事が煩わしく感じられてならない時が在るから
同じ様なものか、と一方的な共感を覚え、敢えて気さくに話しかける事にした。
「お心に甘えて――今日は何の集まりで――?」
私が話し掛けながら出した手は彼に優しく受け止められた。体温でよく暖められた綿の感触がざらりと肌を擦った。
「いえいえ、只の受賞祝いがてら若き才能に肖(あやか)ろうと思いましてな――」
五十半ばであろうか、中尾はその顔に幾多の苦労も渡ってきたぞ、と言わんばかりの 貫禄に満ちた、皺の刻まれた顔をくしゃくしゃにして高らかに笑った。
服は落ち着いた柄の着流しに羽織と到って地味なのだが如何にもこうにも存在が派手だ。
笑い声から表情から佇まいから、何もかも、もうこれ以上洗練出来ませんと云った感じだ。 登り詰めた芸術家と云うものはこんなになってしまうのか、と私は畏怖の念さえ感じた。
「肖るも何も、先生はもう達せられて居られるではないですか!この、戦後廃れ行く運命だった日本の現代絵画がもう一度脚光を浴びたのも
先生の名画の数々のお陰ですし――」眼鏡の李藤が一気に囃し立てる。
「そうですよ、私達が先生から得るものは数知れませんが、先生が我々に肖るなど――」
蒼井さんも真剣に応える。雑記を記す侍の深江はずっと中尾を見つめたままだ。
私は中尾と云う紳士を憐れに思った。
寂しかろうな、などと失礼にも思った。
地位が欲しくて登った者にはこの空間は最上の喜びに満ちているだろう。
崇めて欲しくて、見て欲しくて此処まで登り詰めたのだろうから。
しかし、私には中尾がその類の人間には見えなかった。
周りの人間が口々に彼を褒め称える中、彼は詰らなさそうに深い深い溜息を付いていたから。
一人取り残された子供の様に巨匠は胡乱に相槌などうりながら心は会話から逃れ、壁の作品を眺めていた
「しかし、以前にも見させて頂いたがあの時から輪を掛けて線が感情豊かになっておるな。
まるで流れる旋律の様だ。女性らしく、大胆に、しなやかで透明。実に良い世界だ。」
周囲の賛美を無視して彼は壁に掛かった絵を見渡すとそう褒め称えた。
彼の声は太く強く、よく響いた。
「あ、有難うごっつぁいます!」
如何やら蒼井さんは有難う御座いますと言おうとして緊張の所為か舌が回らなかった様だ。
私は舌を噛み笑いを堪えたが、隣に立っていた野々村はぶはッと盛大に噴出した。 蒼井さんがこちらを見て睨むと
野々村は肩を竦め私の背に隠れた。
「そう緊張しないで欲しい。同じ筆を持つ人間だ」
中尾と言う紳士は蒼井さんの背を何度か叩くとますます彼女は恐縮し有難う御座います――と消え入りそうな声で繰り返した。
「先生、ではそろそろ――」銀縁眼鏡はそう云うと手帳を開いた。
何か予定でも詰まっているのだろうか。
「うん」
〝先生〟は持ち上げられている割には子供の様な返事を返して
私達に挨拶手を挙げ「では、またアトリエにでもおいで下さい」と云うと
背後に三人を引き連れて会場を後にした。
残るは野々村とへとへとに草臥れた遙さんと須藤さん。
それに空気でも抜けたかの様に床にへたり込む、蒼井さん。
受付椅子に座ろうとした遙さんに蒼井さんは
「ご免なさい。お茶、入れてくれないかしら――」と云ったので
遙さんは慌てて腰を上げようとしたが須藤さんはそれを制して自分が行こうとしたが――
「甘やかしては駄目よ、須藤さん。展示会始まる前にも云ったでしょう? 遙はもう自分で働いて、、社会に出なければならないのだから――」
――遥に伸ばしていた手を引っ込める須藤さんの手を優しく掴み微笑んだ後 彼を自分の代わりに席に座らせて遙さんは給湯室へ行った。
彼女も自立しようとしているのだ。でも心配してくれる気持ちも嬉しいのだろう。
だから蒼井の言葉に文句を言わないし、その所業を有り難いとも思っている。
そんな想いがありありと感じられるやり取りに私と野々村は顔を見合わせて微笑んだ。
「ご無沙汰しております。」須藤さんはこちらを向き会釈をしてくれた。
「ご無沙汰しております。お元気そうで――アレから如何ですか?」
須藤さんは少し顔を曇らせると「毎日、手紙が届きます」と呟いた。 我々は何の事か判らずに彼の言葉を待った。
「遙はまだ返事を出した事が無いです。読むには読んでる様なのですが――」
知らぬ内に呼び方が変わっていた。
あの事件以来、彼らの中で関係の変化が在ったのだろう。
仮の父親は真の父親になり、仮の娘は真の娘になりつつ在る中で
欠けた家族の行く先の心配をしているのだろう。
「長い積み重ねで出来た溝です。時間が掛かりますよ」
「――時間で何とかなるのだろうか、と――」
「なりますよ。互いを欲しているのですから。」
「そうじゃな――そうじゃ、そうじゃ。」
老人は思い出したかの様に笑った。
給湯室から帰って来た彼女は受付の机にお茶を人数分置いた。
「椅子がありませんの。立ち飲みで申し訳ないのですが――」
「いえ、頂きます」
私が取り、須藤さんが取り、蒼井さんが取り、野々村が取ろうと机に近寄り
湯のみを取らず、遙さんをじいと見つめた。
盆を抱いたまま俯く彼女に迫る様に一歩近寄る。
迫力に気圧されたのか俯いたまま一歩下がる遙は衝立に背中をぶつけ、背後に逃げる場所が無い事を知る。
前回の二人の関係を思い出して皆が緊張の面持ちで二人を見守っていた。
会場は静寂に包まれ、外の雑踏の音だけが響いていた。
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】