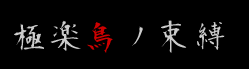【玖話】
「まだ調子悪い?」
目の前の非現実な存在の彼は僕が落とした本を拾い上げ、それに付いた埃を叩き落しながらその表紙を眺めた。
髪が金色に透けてますます異世界の生き物の様に見えた。彼の滑らかに動いた唇を見ながら僕は二度驚いた。
動いている事が不自然な程、彼が余りにも完全すぎた様に――少なくとも僕には眩しすぎてそれを認識する事に酷く時間を要していた。思考が止まる。
「キリコ回想録――好きなのか?あの、なんだっけ――ジョ、、」
野々村はそう言って親指の爪を軽く噛みながら考え込んだ。
「ジョルジョ――」
「ん?」
「ジョル、、ジュ、、デ・、、キリコ、、」
僕は一体何と会話を交わしているのだろうか――
まるで石像か何かに独り言を言っている気分だったが、返事はそんな僕の意識を置き去りにして当たり前の様に返って来た。
「ああ、そうそう。そのジョルジュ――だ。」
興味を持ってくれた事が嬉しかった。
まるでスポットライトが当たったような暖かい温度を伴った高揚感が僕を包んだ。
「好き――だよ。作品の世界観も好きだ。他の油絵の様に無駄に飾り立てて無いと云うか残酷な程、現実的と云うか、決して在る風景と云う訳じゃないんだけどね。焦点がずれていたり、陽の加減にしては影が長すぎたりとちぐはぐでとても幻惑的。でもこの人は。形而上学を語る上に外せない――いや、一番最後に来る人で無いかと僕は思ってるんだ。
形而上学、すなわちこの学問は、、人は産まれてから死ぬまで見る、聞く、嗅ぐ、触れる、味わうと云った五感を働かせ、その全ての情報を受け取り、その人の能力、個性からそれらを選別し人に伝達する、以外にも経験的に語る事が出来ない領域、例えば生き死にとは何たるや、とか、神とは――、愛とは――、人間の存在理由とは――、何て見て、触って確かめたり出来ないだろう?そう云う事を研究する学問なんだけど――」
「知ってるよ。僕だってここの学生だ。」
「ああ、そうだね、ご免。でね、アリストテレスが【存在とは何ぞや】と提示し、ハイデガーが存在と云うものが【成立する条件】を明確にしただろう?そして彼は――」
「――彼は?」
僕は思わず赤面した。僕が心の内に引き篭もり、本に逃避した時から
自分の〝面白い〟が人のそれとは相容れなくなった事を思い出した。
多くの人間は僕の話を聞いて愛想笑いで受け流した後
僕を避ける様になるんだ。
詰まらない話など聞かされた事が余程苦痛だったのだろう。
それも嬉々として語る訳だから話を中座する間も見つけられなかったのかも知れない。
阿呆の様に息継ぎも忘れ捲くし立てる僕は、きっと世間で云う【普通】では無いのかも知れない事を今になって思い出したのだ。
「ご免。詰まらない話を――」
興奮して、また失敗した。僕はいつだって独りよがりだ。
聞きたくも無い話を強要されて嬉しい筈が無いのに――自分の馬鹿さ加減に思わず溜息をついて、力無く席に座った。
「――彼は、の続きは?」
「良いよ、ご免、気にしないで――」
喉元が絞まる。孤独が内臓を押し出して胃酸がこみ上げてくるのを感じる。
今までどうして彼の顔を見れていたのか分からない程に僕は自分の不審な挙動を止められもせずただ、いつもの様に俯き、握った手をガクガクと震えさせた。
「気に成るよ――」
「い、い、や、僕が勝手に興奮して語っただけだから――」
何故か僕は手のひらをぐっと握った。汗で指と指が滑って気持ちが悪かった。
「何だ、折角面白い講談が聞けると期待したのに――」
「面白くなんて無いだろう?」
社交辞令も大概にしてくれ、と内心吐き捨てた後、僕はどうせそう問い詰めたとして本心を話す人など居ないじゃないか、と自嘲した。
他人に何を期待しているのだ、期待などして報われた事等無いじゃないか。
馬鹿な事を、この憤りは明らかに諦めきれない心からの接触を、得られる筈の無い真の心の交わりを今だ夢見ている己の馬鹿さ加減を表している。
「いや、非常に興味深いよ。僕は自分の存在と云うのものの不確かさに不安を抱いて探って追求していく気持ちはとてもよく分かるから」
何を言ってるのか分からなかった。だって彼は明らかに、この室内に居る誰よりも残酷な程、存在しているじゃないか!
僕はそう叫んでしまいたかった――が萎縮しやすく激昂しやすいなんて付き合いたい人間像では無い。むしろその対極だ。彼との付き合いを今、終わらせてしまうのは余りにも勿体無いと思った僕はその自分の心の叫びをぐっと飲み込んだ。
「野々村君は、、存在してるよ。君が存在して居ないなんて云うと僕なんて尚更不安になるよ。触れたら、ほら動く。認識出来るじゃないか」
――そうだ、僕だってそう言う観点では認識して貰えるのだ。押したら動くし、温度も香りも在る。酷い言葉を投げかければ傷つく、、傷ついた、と云う顔は出来ないけれど――
「僕の体が存在しているなんて分かっているよ。ただ、僕の本質は何処に在るのか僕には――分からない」
彼は虚空を見つめ、深刻そうにそう呟いた。酷い話だと思う。彼のその不安が酷く僕の心を浮き足立たせ、彼の孤独がじわじわと心を温めた。
僕はこんな遠い世界の彼も自分と同じ不安を感じる事で不安と云う物が悪い物では無い様な感じがして安心するその裏側で沢山の社会に望まれ、温かく迎え入れられる彼が逃げ場の無い僕の佇む最後の領域、負の範囲(テリトリー)にまで侵食してくる事が酷く図々しく感じてしまい、不愉快にもなっていた。
「君の本質なんて在ろうが無かろうが、君は皆に望まれているじゃないか。恵まれた状況にしては悲観視しすぎだよ」
僕は――嫌な奴だ。
「本質で無いと感じる所で人に望まれても必要とされて居ないのと一緒だよ」
「贅沢だね!」
――これは八つ当たりだ。分かっていても口を止める事が出来なかった。そして完全に論点は、、少なくとも僕の中にあった話の軸からは遠く離れてしまっていた。
妬み、嫉み、そんな類の感情が酷く荒ぶっていた。折角、自分の世界を分かってくれる人が現れたのかも知れないのに…これでは余りにも――
『苛められるには君にも原因が在るんじゃないか?』
世話になった教師の嘗ての言葉は酷い衝撃を持って僕を打ち砕いた。
だって如何したって苛められた。最早自分の力では周囲の動きは止められなかった。原因が分かって、ソレを訂正した所であの悪夢が終結するのなら誰だって如何にかするだろう。
僕はそんなに馬鹿じゃない!そう感じるのなら如何すれば良いか、馬鹿な僕にも分かる様に教えてくれたら良いのに濁すばかりで何も教えてはくれないじゃないか!
この真っ暗闇、渦中に居る僕だけなんだろ?何も分かって無いのは!
分かろうとしてるのに、自分一人の視野では対抗策は練れないし、分かってる筈の渦の外の人は口を閉ざすじゃないか!
――人は一人だ。いくら集おうとも無駄な事だ。何の役にも立ちやしない。
人は人を責めこそすれ、救える様にはなって居ないんだ。それは自分も同じ事。人様の役に立った覚えなど微塵も無い。そんな身だから責められる筈も無く、只僕は憤りを心の奥底に潜め、虚無を胸の中で温め甘やかすばかりだった。
あの時分からなかった答えが今、分かった気がした。
それで無くとも忌まれし者なのに、そんな奴でも構ってやろうと思って手を伸ばせば僻みを隠そうともしない尖った言葉で迎え撃つ。
可愛げも面白みも無い人間だ。もう金輪際近寄らないと思われてしまっただろう。苛められもするさ。
きっと彼に触れてるこの腕も疎まれている筈なんだ。
触るな!と本当は言いたいのかも知れない。
気持ちが悪い!と罵倒してしまいたいのかも知れない。
ただ、人目が在るから、自分の評価を下げないで居る為、僕を憐れに感じる為、出来ずに居るのだろう。
そっと彼から離れた。それでも窓枠は丁度二人分の距離しかなくて
肌が触れ合っていたのが、今度は互いの服の布だけが触れ合っている状態にするのが関の山だった。
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】