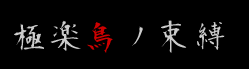【廿話】
ずるずると腹の底を這い回る蛇が憎い。
何故才は我に与えられなかった。
何故才は我に与えられなかった。
雨は枯れた地に呼ばれ降り注ぎ、
太陽は彼を待つ芽に微笑むのにどうして――
在るべく才を妬む。才の存在を渇望する。
ああ、光が見たい。我は生まれながらに盲目だ。
枯れた井戸の底を這いずる蛇の様に私はこんなにも光に焦がれているのに。
才は如何して世の中に溢るるのだ――不幸にも。
我は貪らなくてはならない。次々と欲するままに――
いつまでこうして居るのだろう、此処はまるで地獄だ。
ひとつ、ふたつ、喉元を通り過ぎ――我、みしみしと肥大せり
我をも飲み込んで我は肥大せり
我は器として此処にあらん。
永遠に器と言う呪縛から解き放たれん事を願い、憎む。
幸福とは何処にある物か
光とは幻では無かろうか
クライ クライ イドノ ソコデ ユメヲ タダ ミテイル
***
「お早う御座います」と男所帯に似つかわしくない声が差した。
「はい?――あれ?如何して此処が分かったの?まぁ、上がりなよ」野々村がそう言って勝手に居間に通した。
「失礼します」といつもよりは少し元気の無い――いや、女らしい抑揚で頭を下げ入ってくる蒼井に私は目を細めた。
以前よりも彼女が輝いて見えるのはきっと気のせいではないのだろう。
「いえ、この辺だと伺っていて――朝の散歩を、徘徊していたものですから…」
「いつも君にまとわり付く騎士は居ないね」
「ええ、あの――居ませんね、、」と蒼井は何やら動揺し、頬を染めた。何か進展が在ったらしい。
しかし――
「女性は恋で綺麗になるとは本当なのだね、とても綺麗だ」
「まぁ!そ、それはいつもですわよ!」と彼女は動揺しているのか声を上擦らせながらいつもの様にふざけた。
「――でこんな所まで歩いて来た、と」
「ええ、良い運動になりますわ。お二人も珠には運動しなくてはいけませんわよ」
「こんな朝早くに散歩に出た――と」
お茶を出しながら野々村はそう蒼井さんを問い詰めたから蒼井さんは少し動揺を見せた。
「そ、そうよ。何かおかしいの?」
「ははは、いえいえ。無粋な事を――すいません」
蒼井は頬を紅潮させ顔を伏せた。成るほど、家に居る訳だ。彼女をこうさせている人物が。
「へ、変な野々村さんだこと!」
「いえいえ、新妻が初夜に布団から抜け出したとあっちゃ、新郎は寂しがらないかな?と思ってね」
「野々村!」
「勝手な妄想ですよ、僕の妄想をお話しただけの話です」
野々村の無粋な探りを叱り付けながらも蒼井の反応が気になった。
彼女は図星だったのか首を折れんばかりに下げていた。
「だって…」
「ん?」
「ど、どんな顔をして会ったら良いか分からないのですもの!」
「どんな顔って…」
女性特有の感情なのか、私も野々村も顔を見合わせ困惑した。理解が出来ないのだ。
「おはよう」と言って笑えば良いと思うのだけども…女性はまぁ…
「今の顔のままで良いんじゃないのかな、その恥らったままの…」
「怒りますよ!」と何故か蒼井は机を叩き怒った。
「まあまあ」と間に入る野々村がまた趣味の悪い事を提案した。
「取りあえず送っていくよ」と言った後「あのすかした男の幸せ顔も見てみたい気がするし」と笑った。
結局嫌がる彼女を何とか宥め、最初彼女の言った通りに運動する羽目になった。
彼女の家までは若干遠く、一時間程であろうか大いに日差しを浴びて光合成をした。
相変わらず蒼井と野々村はふざけ合っていた。
笑う野々村の顔はあの夜見せた顔と相まって少し胸の訳の分からない苦しさが中和された様な気がした。
結局記憶を探っても探ってもあの夜彼が言った事に思い当たる所が無く
時間が経つにつれあれは夢だったのでは無いだろうか、と言う気さえしてきていた。
笑ってれば本当に年相応な青年なのだ、彼は。
ふっと彼の部屋を、あの風景を思い出す。酷くとっ散らかり物や本が散乱する中
彼はまるでそれらに埋もれる様に横たわり、裸体のまま毛布に縋り付く様に胎児の様に丸まって寝ていた。
人ならざるもの、の様な気がして怖くて思わず開けていた襖をそっと閉じた。
見てはならぬものを見た様な背徳感が全身を覆った。
美術品の様な美しさ故に、と言う訳ではない。むしろ――洋書に出てくる「ほむんくるす」とか「ふらんけんしゅたいん」とか言う
タブーとされる人造物的な印象だった。
今こうして蒼井と話している姿を見ると実に人間らしい。日常、だ。平和、だ。
彼は一体――何者なのだろうか…。
「さぁ、教授。足音を立てましょう。彼がまだ裸で居たら気まずいので誰か尋ねて来たぞ、
と言う事を大いに知らせなくてはいけません」
「まったく君は、大人なのか子供なのか分からないな」
「本当に――ね」
蒼井は笑って玄関の鍵を開け戸を開けた。
家の中では物音一つしなかった。
「ただいま――」
返事が無い。蒼井は恐る恐る寝室を見に行くが居ないらしく玄関に居る我々を振り返り首を振った。
少し急ぎ足で居間を覗き、そしてアトリエにしている土間へ向かい――妙な声を上げた。
「ひ!」
「如何し…」
「様子が…」
ゆっくりと靴を脱ぎ、彼女がふらふらと入って行った土間へと向かう。
そして覗いた風景は――まさに誰かの書いた抽象画の如く奇妙な風景だった。
壁際には白い布を掛けられた絵が沢山並び、土壁を沢山の油絵の具が極彩色に彩り、
そして蒼井であろう少女が微笑むキャンバスは大きく裂かれ、その前に珠城だろう人物が座っていたが
その体には首が無かった。
蒼井には分かるのだろう、イスに座る体が誰の物か。誰だったモノか。
恐怖で歯の根が合わないのだろう、蒼井は歯をガチガチと振るわせた。
「野々村、蒼井さんを!」
「さぁ、少し別室へ行きましょう、蒼井さん」
「嫌!嫌よ!如何して――これからじゃない!全部これからじゃない!如何して!」
急に叫ぶと泣きながら笑い始めた。
「やだ!嫌だわ!もう!嘘でしょ?きっと嘘!ふざけないでよ!あはは!驚いた!珠城さんったら冗談が過ぎるっ!」
蒼井はそう言ってその血に濡れた肩を揺さぶると――ゆっくりとその体は床に落ち、鈍い音を出した。
それと同時に蒼井は祈る様に手を組むとゆっくりと膝を付き倒れそうになったのを野々村が抱きとめた。
「気を失ってます」
「無理も無い、寝室へ…」
「はい」
野々村にそう指示をして私は土間を見渡した。足跡はあちこち踏み荒らされていて分かり辛いが
真新しい足跡が直接土間へ入れるだろう勝手口に続いていた。
余り歩き回っては現場を荒らす事になるだろうが確認だけ、そっと勝手口の扉を開けると鍵は中から開いていた。
元々警戒態勢にあった蒼井が戸締りを怠って出て来るのは不自然で
だとすれば蒼井が外出後、誰かが入ってきた事になるだろうし首がない時点でそれを処理した人間が居る訳で――
要するに犯人は堂々と玄関から入り、殺害後此処から出た訳だ。
取りあえず樋口に連絡した方が良いな、電話は繋がっているだろうか――
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】