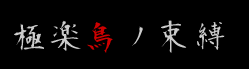【拾玖話】
浮き足立つのは私らしくない。
ましてやあんなに分かりやすい遊び人にほだされてしまう等…
ランプに明かりをつけながら蒼井は新作を書こうと真っ白なキャンパスを掲げ先程の事を思い出していた。
ましてやあんなに分かりやすい遊び人にほだされてしまう等…
ランプに明かりをつけながら蒼井は新作を書こうと真っ白なキャンパスを掲げ先程の事を思い出していた。
『蒼井さん、君が傍に居てくれたら…』
私の手をうやうやしく取り懇願する様に顔を覗き込んできた。
バーのランプがゆらゆらと珠城の端正な顔を照らした。
その光と影との造形が酷く嘘事のように綺麗に見えた。
胸が苦しくなるのはきっと、室内の煙草の煙のせいだろう。
ふわふわと景色が揺らいで見えるのはきっと先ほどまで歌っていた彼の異国を思わせる歌に酔っているのだろう。
こんな時に心を開放すべきではない。流されてしまうのは頂けない。
彼がその先にどう続けようとも私は考える時間を乞うのよ。
彼がつむぐ言葉はきっと…とても重要な契約の様な気がするから――
「いずれは音楽で身を立てます。それまでは絵で…こんな時代ですがなるたけ苦労はさせません。
二人なら何とか、三人でも…何とか。四人なら…もし食わせられないのなら僕は砂でも食べて…」
彼は自分の言葉に照れた様にふっと言葉を切って笑った。
私もつられて笑いながら何故か泣きたくなっていた。
「どうか僕の傍に…その…ずっと…」
「…それはどう言う…」
「だから、ああ!言葉が邪魔だな!何て言えばいいんだろう。その…結婚を…」
それ以上言葉が出ないのか、彼は肩を潜めて言葉を切り、困った顔で笑った。
私は「考えさせて下さい」と言った。まるで三文劇。だって心の中でもう考えてなど居ないのに――
はい、と言う顔を大いにしていただろうに。
「そ、そ、うだよね。いきなりこんな事を言われてもね、分かってる、待ってるよ。でも
玄関で番人位はさせてくれるよね?でないと心配で家に帰っても寝られやしないよ」
真顔でそんな事を言うので私は思わず笑ってしまった。
そして――差し伸べられた手を始めて握った事が今の所出来る精一杯の「はい」だという事は
きっと彼には伝わらないのだろうと思った。
器用な割りに、何処か鈍い人だから。妻になったらきっと苦労するわね、と心中で笑った。
店を出ると夜空にぽっかり穴の開いた様な見事な月が浮かんでいた。
「吸い込まれそう」と私が笑うと
「一緒に空を飛びますか?」と彼は笑い透き通った声で不思議な歌を歌った。
「あちら(外国)で流行っているそうだ。店に居た外国人に教えて貰ったんだ」
「素敵な曲ね」
「そうだね。日本ももっと素敵な音楽を楽しめる様にならないとね」
「貴方の役目ね」
「頑張るよ」
彼はそう言って歌声を月に吸い込ませた。
すれ違った外人の兵隊さんが彼の肩を持ち引きとめた。
何か分からない言葉で話しているが人差し指を立てているのでもう一度歌ってくれとねだってるのだろう。
彼はそれを察してもう一度、さっきの不思議な曲ともう一曲、
外国を思わせる歌を歌うと兵隊は掌で自らの涙を擦り取りながら彼に何枚かのお金を握らせ、去っていった。
「何て言うお歌だったの?」
「Home on the Rangeと言う曲らしい。故郷を偲ぶ歌だよ」
「そう…」
「帰れる場所があるのに離れる何て、寂しいだろうと思ってね」
月は変わらずぽっかりと浮かんでいた。何となくそれを仰ぎ見ていた。
「僕たちは幸せだよ、蒼井さん。まだまだ戦争の痛手は残っているけど我々は生きている。
いくらでも、白いカンバスに絵を描く様にこの国を作れるんだ」
「そうね」
「僕に難しい政治の話はわからないけど…」
「心を動かせる」
「まだまだ非力だけどね。色んな世界を色んな人に見せてあげたいんだ。
生きて死ぬだけの人生だよ。色んな事を知って、悲しんで泣いて。喜んで笑いたいじゃないか」
「そうね、その通りよ!」
「生きた意義と言うのをそう無理やり解釈してるんだ、僕は」
「無理矢理だなんて!」
私たちは笑いながら帰路に着き、玄関で「此処で見張ってますから!」とふざけて敬礼した彼の手をぐっと引き寄せ家に上げた。
「風邪を引かれたら溜まりませんもの」
「狼になるかも知れませんよ?」
「これが――先程の答えとはお思いになりませんか?」
彼は一瞬驚いた顔をした後、喜びを隠し切れない…隠す気も無いのかも知れない。
玄関先で万歳を三唱されてしまった。
「た、珠城さんったら!」
「だってこんな!こんな嬉しい事!はっはっはっ!」
「何故笑うのよ!」
「嬉しいから笑うんだよ、しょうがないじゃないか!」
凄い勢いで喜んだ癖に、私の手を取るのは本当に恐々で…
まるで割れ物にでも触る様にそっとそっと、彼は私を抱きしめ、何度も良いのですが?と問いながら接吻をした。
男性に触れられるのはこれが初めてで――
彼は酷く優しく丁寧に触れるのが酷くくすぐったく、そして幸せだった。
行為の後に「こんな幸せ、在っても良いんだろうか…」と繰り返し私の肩を撫ぜ、何度も抱きしめる彼が眠るまでずっと私は彼を眺めていた。
そして今――私は始めての人物画を描いている。
ランプに照らされた彼の裸体の美しさを、幸せをかみ締める彼の表情を、そしてもう隠し切れない、この胸にたぎる幸福を――
いつの間に朝になっていたのか、鳥の声でそれを知った。
彼にこの胸の内を知られるのが恥ずかしくて、そしてくすぐったくて、何となくその絵を端に寄せ、心持ち隠した。
寝室へ向かいすやすやと無垢な顔で眠っている彼の顔を眺め、その頭髪を朝日が黒から赤茶色に変えていく様にしばらく見蕩れていたが顔を合わせるのが何となく恥ずかしくなって早目の朝食だけを食卓に乗せて散歩に出かける事にした。
――それが彼との最後だった。
【続く】
【続く】

私の手をうやうやしく取り懇願する様に顔を覗き込んできた。
バーのランプがゆらゆらと珠城の端正な顔を照らした。
その光と影との造形が酷く嘘事のように綺麗に見えた。
胸が苦しくなるのはきっと、室内の煙草の煙のせいだろう。
ふわふわと景色が揺らいで見えるのはきっと先ほどまで歌っていた彼の異国を思わせる歌に酔っているのだろう。
こんな時に心を開放すべきではない。流されてしまうのは頂けない。
彼がその先にどう続けようとも私は考える時間を乞うのよ。
彼がつむぐ言葉はきっと…とても重要な契約の様な気がするから――
「いずれは音楽で身を立てます。それまでは絵で…こんな時代ですがなるたけ苦労はさせません。
二人なら何とか、三人でも…何とか。四人なら…もし食わせられないのなら僕は砂でも食べて…」
彼は自分の言葉に照れた様にふっと言葉を切って笑った。
私もつられて笑いながら何故か泣きたくなっていた。
「どうか僕の傍に…その…ずっと…」
「…それはどう言う…」
「だから、ああ!言葉が邪魔だな!何て言えばいいんだろう。その…結婚を…」
それ以上言葉が出ないのか、彼は肩を潜めて言葉を切り、困った顔で笑った。
私は「考えさせて下さい」と言った。まるで三文劇。だって心の中でもう考えてなど居ないのに――
はい、と言う顔を大いにしていただろうに。
「そ、そ、うだよね。いきなりこんな事を言われてもね、分かってる、待ってるよ。でも
玄関で番人位はさせてくれるよね?でないと心配で家に帰っても寝られやしないよ」
真顔でそんな事を言うので私は思わず笑ってしまった。
そして――差し伸べられた手を始めて握った事が今の所出来る精一杯の「はい」だという事は
きっと彼には伝わらないのだろうと思った。
器用な割りに、何処か鈍い人だから。妻になったらきっと苦労するわね、と心中で笑った。
店を出ると夜空にぽっかり穴の開いた様な見事な月が浮かんでいた。
「吸い込まれそう」と私が笑うと
「一緒に空を飛びますか?」と彼は笑い透き通った声で不思議な歌を歌った。
「あちら(外国)で流行っているそうだ。店に居た外国人に教えて貰ったんだ」
「素敵な曲ね」
「そうだね。日本ももっと素敵な音楽を楽しめる様にならないとね」
「貴方の役目ね」
「頑張るよ」
彼はそう言って歌声を月に吸い込ませた。
すれ違った外人の兵隊さんが彼の肩を持ち引きとめた。
何か分からない言葉で話しているが人差し指を立てているのでもう一度歌ってくれとねだってるのだろう。
彼はそれを察してもう一度、さっきの不思議な曲ともう一曲、
外国を思わせる歌を歌うと兵隊は掌で自らの涙を擦り取りながら彼に何枚かのお金を握らせ、去っていった。
「何て言うお歌だったの?」
「Home on the Rangeと言う曲らしい。故郷を偲ぶ歌だよ」
「そう…」
「帰れる場所があるのに離れる何て、寂しいだろうと思ってね」
月は変わらずぽっかりと浮かんでいた。何となくそれを仰ぎ見ていた。
「僕たちは幸せだよ、蒼井さん。まだまだ戦争の痛手は残っているけど我々は生きている。
いくらでも、白いカンバスに絵を描く様にこの国を作れるんだ」
「そうね」
「僕に難しい政治の話はわからないけど…」
「心を動かせる」
「まだまだ非力だけどね。色んな世界を色んな人に見せてあげたいんだ。
生きて死ぬだけの人生だよ。色んな事を知って、悲しんで泣いて。喜んで笑いたいじゃないか」
「そうね、その通りよ!」
「生きた意義と言うのをそう無理やり解釈してるんだ、僕は」
「無理矢理だなんて!」
私たちは笑いながら帰路に着き、玄関で「此処で見張ってますから!」とふざけて敬礼した彼の手をぐっと引き寄せ家に上げた。
「風邪を引かれたら溜まりませんもの」
「狼になるかも知れませんよ?」
「これが――先程の答えとはお思いになりませんか?」
彼は一瞬驚いた顔をした後、喜びを隠し切れない…隠す気も無いのかも知れない。
玄関先で万歳を三唱されてしまった。
「た、珠城さんったら!」
「だってこんな!こんな嬉しい事!はっはっはっ!」
「何故笑うのよ!」
「嬉しいから笑うんだよ、しょうがないじゃないか!」
凄い勢いで喜んだ癖に、私の手を取るのは本当に恐々で…
まるで割れ物にでも触る様にそっとそっと、彼は私を抱きしめ、何度も良いのですが?と問いながら接吻をした。
男性に触れられるのはこれが初めてで――
彼は酷く優しく丁寧に触れるのが酷くくすぐったく、そして幸せだった。
行為の後に「こんな幸せ、在っても良いんだろうか…」と繰り返し私の肩を撫ぜ、何度も抱きしめる彼が眠るまでずっと私は彼を眺めていた。
そして今――私は始めての人物画を描いている。
ランプに照らされた彼の裸体の美しさを、幸せをかみ締める彼の表情を、そしてもう隠し切れない、この胸にたぎる幸福を――
いつの間に朝になっていたのか、鳥の声でそれを知った。
彼にこの胸の内を知られるのが恥ずかしくて、そしてくすぐったくて、何となくその絵を端に寄せ、心持ち隠した。
寝室へ向かいすやすやと無垢な顔で眠っている彼の顔を眺め、その頭髪を朝日が黒から赤茶色に変えていく様にしばらく見蕩れていたが顔を合わせるのが何となく恥ずかしくなって早目の朝食だけを食卓に乗せて散歩に出かける事にした。
――それが彼との最後だった。
【続く】
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】