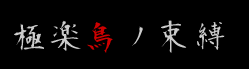【拾弐話】
「【街の神秘と憂鬱】――確かに憂鬱だな」
僕は笑った。彼も僕を横目で見て笑った。
言葉が出ないけどそれが不思議と苦痛では無かった。
「さっき君が言ってた明暗云々は――」
彼はそう言って絵の端に描かれた少女を指した。
「そうだね、この構図だとこの少女が影として描かれているのが変だ
でも彼は五感を超えた感覚で物事の本質を捉えて――」
「うん――分かる。視点も…何処を中心に捉えたら良いのか――ずらしてる?」
「多視点描画と言うそうだよ」
「成る程」
傍から見ればおかしな風景だったに違いない。
大の成人男子二人が一つの本を覗きあってなんだかんだと話してる。
僕が覗き込むとまるで陣地取り合戦の様に彼は肩で僕を押し返す。
「そもそも、、僕が読んでた本なのに――」
「だって君が僕の興味を引く様な話し方をするからだろう?」
「君が話せって言ったんじゃ――」
「そもそも君が勝手に話しだして止めたりした癖に。それに君がこんなに面白い事を知ってるとは知らなかったんだよ、今まで言葉なんて発しなかったじゃないか。隠し持って一人で楽しんでたなんて――意地悪だよ」
「隠してた訳じゃ――」
彼は憮然とそう言い放って僕の持ってた本を読んでた。
僕は一緒に本に目を落としながらずっと彼がこっちを向かない様に祈ってた。
だって変だろう?こんなににやにやと頬を緩めてるなんて。きっと変態だと思われる。変なんだ、僕は。
だって彼が僕の与えた情報にこんなに興味を示してくれるなんて、こんな子供の様なやり取りが出来るなんて、何よりも僕がこんなに人と話せるなんて。
そうだ、僕は〝人〟だったんだ。
普通の人ならこんな事、忘れはしないのかも知れない。
でもずっと人から拒絶されて影を好み、光を怖がり、肩を縮め存在を消そうと努力する僕にはこんな事を今更思い出す程、胡乱になっていた。
背中を窓を通った日光が照らす。まだ春だと言うのに暑いくらいだ。
こんなに日の光が温かかった何て、そんな事にも気が付かなかった。
背後の窓に嵌った硝子越しに外に居る学生達の声が聞こえる。
楽しそうに笑っていた。振り返ると煌々と土埃の溜まった窓から光が差し込み風が優しく木々を揺らし軽やかに去っていった。
季節の移り変わりにさえ俯き、閉ざして居た事に今の今まで気が付かなかった。
「有難う恩村。楽しかったよ。これ図書館のだろ?」
「――え?、、うん」
「返す時教えて。誰かに借りられる前に借りたい」
彼はすくと立ち上がり、本を目の前でひらひら振ると僕の膝に置いた。
「授業かい?」
「いや、野暮用。知り合いが個展を開くんだ」
――君も来るか?――なんて言葉を正直期待した。
でもそう言われても僕は警戒して断ったに違いない。
でも僕は絵が好きだと言ったばかりなんだけど、、
とはいえ「僕も連れて行って」などと言う勇気は無い。
だから僕は複雑な顔をして
「そう――」と呟くだけだった。
「じゃ、またね」
彼は当然の様に身を翻して去っていく。
僕は広くなったその場所に取り残され、余った場所を持て余し、急に居心地が悪くなったのを感じた。
今の今まで気にならなかった雑音が――迫り来る。
椅子を引く音、鉛筆を研ぐ音、咳払い、笑い声、本を捲る音。
――視点も…何処を中心に捉えたら良いのか――
不意に頭を過ぎるさっきまでの隣人の声。
彼が傍に居て、彼を見ている時は彼に視点が在っていたけど
こうしてまた一人になると僕は、、何処を見て良いのか、何を聞いて良いのか分からない。
多視点描写は日常だ。酷く不安になる。ならせめて現実逃避として違う世界を望めば良いものを矢張り僕は鏡や不安定な絵に惹かれ、日常と同じ様な不安と接したがる。
野々村君との時間はそんな不安だらけの日常の中で唯一、視点のはっきりした時間だった。
僕は更なる彼との対話を望んでしまう自分を押し込める為に沢山の言葉を自分に投げかけた。しがみ付くな、嫌われてしまう。期待するな、傷ついてしまう――
でもまた――
話せたら良いな――
ぐっと彼から返して貰った本を胸に抱き、僕は研究室を出た。
当ても無く、只ごみごみと蠢く人の気配から抜け出したくて水面に呼吸をする如く廊下に出ただけの話だった。
不意に自分の背にする研究室の隣に扉が開く。
六華教授の資料室を兼ねた応接間である。
「――しぶりだからお昼でもご一緒しようと思ってね。それに君をつれて来て欲しいと彼女からのたっての願いだから」
「僕だって行きたくない訳では在りませんが引っ掛かる事も在りましてね」
「遙さんの事か?」
六華教授と不愉快そうな顔をした野々村が何やら話しながら出てきた。
本当なら今から擦れ違う野々村に「さっきは――」「また――」とか気さくに言えば良いんだろうけど生憎どんな顔をしてどんな声で、どんな態度でそんな言葉を発するのか分かりかねる僕は先程の楽しい時間を悔いる程、関わった事を後悔していた。
知り合いが出来ると何か特別な事をしなくてはならない気がする。
きっと知り合いと思ってるのは僕独りなのだろうけど、もしそうじゃなかった場合を考えると胃が痛くなり、思わず本で顔を隠し廊下の壁と不自然に一体化する。
目の前を通り過ぎる二人。嫌らしくも聴覚は過敏と言って良い程、僕は聞き耳を立てていた。
「前の事件以来だから」
「何の連絡も無しですよ」
野々村は小気味良く笑っていたから怒っている訳では無さそうだった。
「犠牲も大きかったからな――顔も出しにくいのだろう」
「警察からお咎めは無かったんですか?」
「直接は何もして居ないから――あの状況では誰も責めなかっただろう」
「だから自ら追い込んで、縮こまって連絡もしなかった訳で」
「解かってあげて欲しい」
「いや、解かってますよ」
遠ざかる野々村の笑い声が意地悪い響きを持って廊下を木霊する。
「さあ、どうしてやろうかな」
「お手柔らかにな、お兄様」
教授は柔らかく笑った。
二人が何をするのかが気に掛かって居ても立っても居られなかった。
結局の所、僕は卑しい真似と知りながら二人の後を付け――今に到っている。
相変わらずざわざわと騒音の絶えない人ごみの中、
僕はいつの間にか道の端に座り込んでいた。
目の前には野々村の知り合いが開くと言う画廊だろうか、彼らは向かいの喫茶店に入ってしまい卑しい真似をして居る僕が入ってその卑しさを知らしめるのも忍びなく
ただ、興味を惹かれて雑踏に紛れながら画廊に踏み入った。
壁には繊細なタッチで描かれた濃紺の海空、飲み込まれる様な引力を持つ月――そして月光で透かされた桃色の花弁が悲しげに色を様々に変え、脆く、鮮明に生きる様が描かれていた。
嗚呼、小波が聞こえる様だ。光の飛翔が甲高い音を立てて広がっていく。
視点の安定した悲しさだ、止められぬ時の慟哭だ
赦されざる罪の贖罪への憧れだ。これは――
「お分かりになりますか。お若いの」
不意に肩に手を掛けられて筋肉が勝手に跳ねる。
「は、は、はい?――はい!」
「見事な作品だ」
落ち着いた柄の着流しに羽織を羽織った品の良い中年男はそう言って
何とも複雑そうな顔をしてゆっくりとしみじみ言葉を出した。
「素晴らしい」
「――本当に、僕もそう思います」
「ん」
男は大きく深呼吸する様に絵に感嘆の溜息を付くと
一瞬だけ眉間に皺を寄せ苦しげな顔をした。
「苦痛――ですか?」
何故そんな事を見ず知らずのこの人に聞いたのかは自分でも分からない。
ただそれを受けてその男は「どっちも――」と笑った。
人生の年輪の様な顔だった。一字一句深みを感じさせる不思議な人だった。
男は僕に軽く会釈すると小走りに駆け寄ってきていた眼鏡をかけた男が額の汗を拭きながら彼の背中を押す様にして誘導し、女性に引き合わせていた。腰まで伸ばした真っ直ぐな黒髪を無造作に束ねた質素な女性。洋装が勿体無い程の姿勢で深々と男達に頭を下げ、壁に掛かる絵を案内していた。
綺麗な人だった。凛とした姿はまるで
百合の様に高潔さを感じさせた。
ここは僕には相応しくない場所だと痛感した。華やか過ぎる。
彼女も男も有象無象の人間達も。その華やかさに酷く憧れを持ちながらも
異世界に棲む僕はその場自体が息苦しく感じて仕方なかった。
雑踏に紛れそそくさと外に出て壁伝いに歩くと目の前を同じ様に歩いていた
猫背の――僕が言うのも躊躇うけど、陰気で不審な男が目に入った。
今日の予定は何も無い。
いつもなら今頃篭っている図書館も今日は何故か行く気がしなかった。
気になるは目の前の僕の様な男。視点が彼に合ってしまった。
まるで世界が彼を中心に描かれている様に見えた僕は――
怪しまれない距離を取りながらそっと彼の後を歩く事にした。
【続く】

【NEXT】/【BACK】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】


Special Thanks to …Crip Art by 退廃メトロノーム/Template Designed by I/O