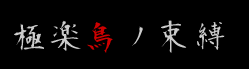【壱話】
此処は真っ暗闇である。
清清しい程 光の届かぬ、視界ごと密閉された世界。
色彩は無い。淀みきった空気がへばりつく様に体に纏わり付き
私の内部にて切なく身を捻り切る様に体内を蠢く粘液が在るだけだ。
此処は悲しい程に凡庸な我が身を嘆く事から目を背ける対象も持たず
途方も無く長い時間止められぬ自己嫌悪に翻弄され続ける無間地獄である。
才が在る人を見る度に思う。
自分に才の無い事ぐらい判っているのに思う。
分かっているから思う。
如何してそれは私が賜った才では無いのだろう
思い切り手を伸ばそうとも、寝る間を惜しんで精進しようとも
何も届かない、指先にすら触れない。
それもその筈、棲んでいる次元さえ違う。
分かっては居るのに幻の様に蕩う其れに手を伸ばす事を止める事が出来ぬ。
才に思わず鳥肌が立ち、ひれ伏す自分を殺してしまいたくなる。
内なる嫉妬が荒れ狂い、無力承知で筆を取るが書けども書けども満たされる事も無く、
只少しの進歩が心を引きずり努力を重ねればひょっとしたらあの鬼才の様になれるだろうか、などと虚しい希望を抱くのだ。
嗚呼、暗い、此処は暗い。光が当たらず、じめじめとして居心地が悪い。
まるで粘菌の巣窟だ。蔓延る。形振り構わず侵食して来る何かを感じる。
脆弱な私など喰われて仕舞う。
そんな恐怖が私の心を微かに光の漏れる上へと望ませるのだ。
何と私は小さいものか。
矮小で、無力で、――風にさえ掻き消されてしまいそうだ。
風さえ吹かぬ穴の中で身を縮める事さえ出来ずに
極彩色の光の園を夢見るのだ。
深淵の底深く。
ぽっかり見える光が憎い。
嗚呼、此処は真っ暗闇である。
***
ざわざわとした空間。
品の良い色彩が右へ左へ闊歩する。
黒、浅葱色、びろうどの様な光沢の赤、黒。
和装、洋装、若者、老人、女性、男性、――
国内に居る全ての種類の人間を集めてきたのだろうかと
思う程、会場は個性的な人間で満員になっていた。
みっしりと詰まる会場を目に私と野々村は顔を見合わせ
中に入る機会が見つかるまで会場前の喫茶店で時間を潰す事を
暗黙の内に決め、どちらとも無く足を動かし、其処に向かった。
些か焦げ過ぎた黒に近い色の茶けた戸を押すと
扉に付いていたのか大きな鈴がからんからんと間抜けに鳴った。
「いらっしゃいませ」と戸から真っ直ぐ伸びた様なカウンターから
白髪の年の割りに背の真っ直ぐ伸びた初老の男が声を掛けた。
白い開襟シャツの上に黒く袖の無い胴着、
如何にも私が店員だと主張しているその姿で初老の男は盆に水を乗せて
私達を席に案内しようとカウンターと窓際の机を交互に手の平で差した。
私達は窓際を指差すと彼は微笑み、「ではこちらへ」と
席へ先導し、私達を其処に座らせて洒落た硝子の器を置いた。
「私は珈琲を――在るならモカで。彼はアメ――」
「僕は紅茶を――」
私はこの所、寝る時間の遅く、起きる時間が早い彼に
不眠の疑いを持っていたから薄いアメリカンを飲ませるつもりだった。
それを遮り、彼は紅茶を頼んだ。その事が引っ掛かった。
我が家に紅茶は置いていない。
このご時世、紅茶も珈琲も生活必需品とは離れた嗜好品で値の張るものだし
珈琲は目覚ましに飲むが紅茶は特にといって必要だとは思わなかった。
「施設でも紅茶を?」
「いえ、飲んだ覚えは無いです。でも口が勝手に――」
彼は首を傾げ考え込んだ。
私はその事を手帳に記そうとして胸元に手を突っ込んだが彼は
手でソレを遮り、微笑んだ。
「これは僕が自分で覚えておきます。大丈夫です。」
「でも欠片は集めて纏めて記した方が全体像が見えやすいだろう?」
「教授が覚えて下さったり、記して下さったりしてる、と安心してしまうと
僕の記憶から抜けていきそうで――」
彼は頼りなく肩を狭めて笑った。
私はそっと胸元から何も掴み出さずに手を抜いた。
「いつもお心使いに感謝してます。」
「ん――。」
珈琲豆が挽かれたのだろうか、店内に渋みと酸味の混ざった濃厚な香りが漂った。食器の擦れ合う高音と店内に流れる異国の音はとても相性が良く気持ちが良かった。
向かいに見える展示場では相変わらずみっしりと詰まった人が蠢き
その間から僅かながらにちらちらと蒼井さんの姿が垣間見えた。
――彼女も此処から見ていたと言っていたな。
そんな事を思い出したのを切欠に私は以前巻き込まれた事件に思いを馳せた。
幻想ノ櫻事件――
(些か浪漫に満ちすぎた名前だが私の脳裏に残る印象を言葉にすると
そうなるのだからしょうが無い)
と私は呼んでいるのだが、その事件の重要関係者が今、目の前で
忙しくしている蒼井さんを嘗てこの店で、この位の時間帯に見ていた筈であった。
彼女はどんな思いでこ風景を眺めていたのだろうか――
癒え得ぬ孤独を抱いて、酸素を求める魚の様にバスを乗り継ぎ
街へ出かけ――
誰も助けてはくれぬと思う彼女は当てにならぬ人間が大勢行き交うこの雑踏でたった一人、どんな事を思っていたのだろうか。
「前の件ですか?教授」
「まあ、な」
「きっと彼女はここで――迷っていたのでは無いでしょうか」
「迷って?」
「ええ。迷いは在ったと思います。あの様子だと――割り切りの巧い方じゃない」
「だから――蒼井さんは許したのだろう」
「許して――無いですけどね――」
彼は苦笑しながら硝子越しに展示場を指差した。
少し客足が捌けて来たのか場内が少し垣間見えた。
その場内では蒼井さんと何やら汗をかき、忙しなく筆記や客の案内をしている遙さん、そして売却済みの札を貼っては絵を壁から外し、また新しい絵を掛ける須藤さんの姿が見えた。
「鬼だね、蒼井さん。」と野々村は笑った。
「働きにも出た事の無い良家のお嬢さんに何たる荒修行を――」
私もそう云って笑った。
懸命に、布巾を用意する暇も無いのか遙さんは袖口で額の汗を拭った。
そんな遙さんが心配なのか須藤さんは何度も何度も彼女の様子を見て
心配そうな表情と誇らしげな表情を繰り返しては「手が止まってます!」と
蒼井さんに激を飛ばされるのか慌てて作業に戻る、を繰り返していた。
「真の父親――なるほど、こうして見ると本当だ。」
野々村は以前話した事を思い出したのか嬉しそうに納得した。
「彼が居るから、きっとまた身を寄せ合って生きれるさ。」
「そうですね。」
不意に耳元で食器が鳴る音がした。
【続く】

【NEXT】/【狂人ノ舞:目次】/【GALLARY MENU】/【SITE TOP】